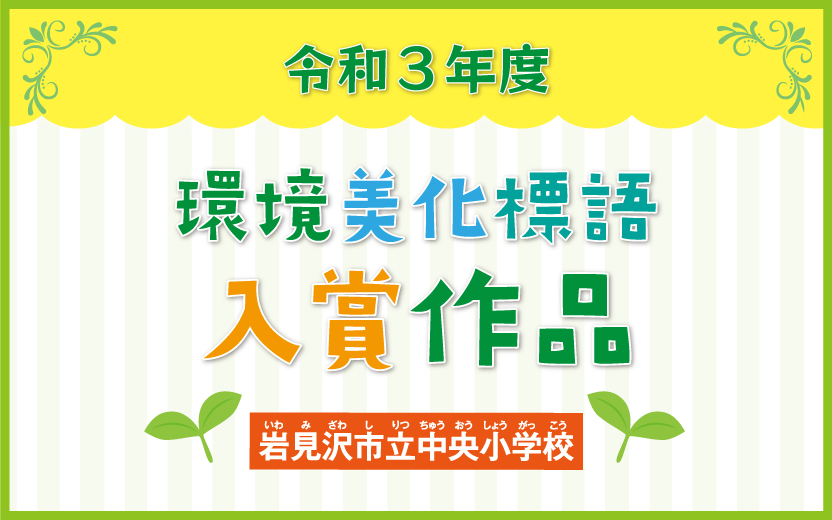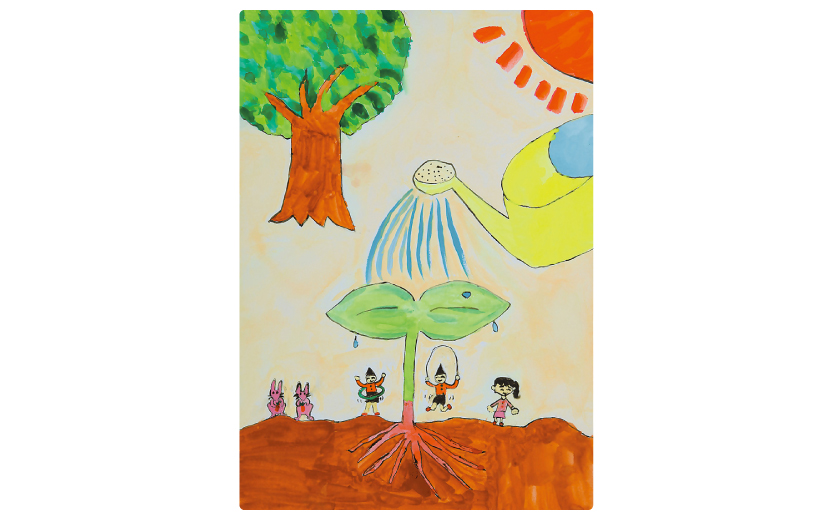目次 [非表示]
研究所で働いていた知識や経験を活かして、「大阪市域生き物調査」や「小学校生き物さがし」のお手伝い、「自然体験観察園」の管理や講師をされている桝元さんにお話を聞きました。
今月のテーマ:身近な自然環境について考える
たくさんの種類の生き物が支え合って生きていることを生き物観察で知ってもらいたい

大阪市エコボランティア
桝元 慶子さん
大阪市立環境科学研究所で約40年研究職として勤務。現在は大阪公立大学大学院客員教授、阪南大学非常勤講師として、共同研究や若手の育成にあたる。
長く環境教育事業に関わり、大阪市エコボランティアとして、気候変動や生物多様性の分野で、環境行政の支援をしている。
ごく普通の生き物もくまなく長い目で
これまで、大阪市内の155校の小学校で、生き物さがしの授業を行ってきた桝元さんは、さまざまな環境に関するプロジェクトに参加しています。
「多様な生物との関わり合いについて学べる『自然体験観察園』では、園内の種から芽ぶいた実生のなえを育てて林をつくるプロジェクトや、都市に失われつつある、多様な虫や鳥たちがやって来る草地を再生するプロジェクトを行っています。
他にも、市内を歩き回って生き物を調べて記録したり、撮影したり、標本採集をしたりしています。大都市である大阪は、外来種の動植物が持ちこまれる機会が多く、環境の変化も激しいため、在来種が追いやられています。それに気が付けるよう、私は道端のごく普通にいる生き物も、くまなく長い目で記録するよう心がけています。」
生き物観察で気付いてほしいこと
桝元さんに読者へのメッセージをお聞きしました。
「みなさんは、『雑草だから』『害虫だから』と生き物を殺してしまっていませんか? 本当はたくさんの種類の生き物が支え合って生きていることに、私たちはなかなか気づけません。人間も周りの生き物に生かされていることを心にとめて、いろいろ調べて考えてみてください。」
エコチルは、地球環境保全に取り組む子ども達を育むとともに、学校や家庭でのエコライフ推進を目的としたメディアです。













 シェアする
シェアする つぶやく
つぶやく 送る
送る 前の記事
前の記事